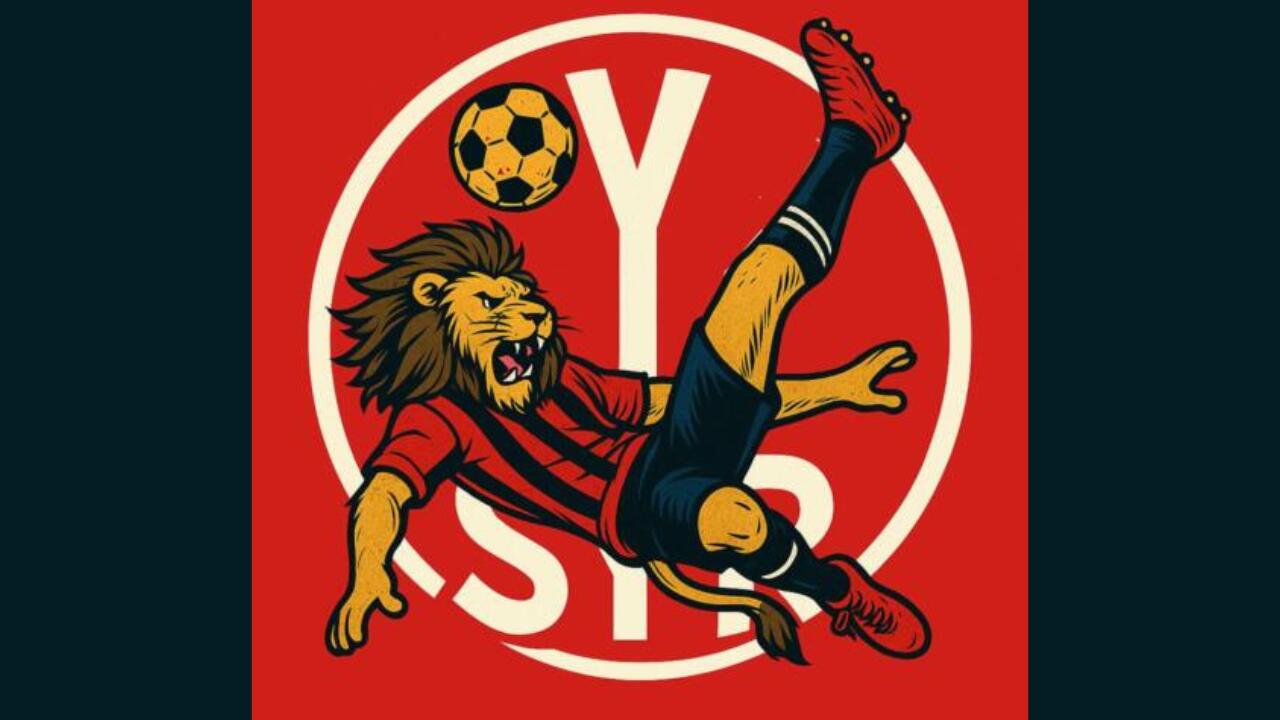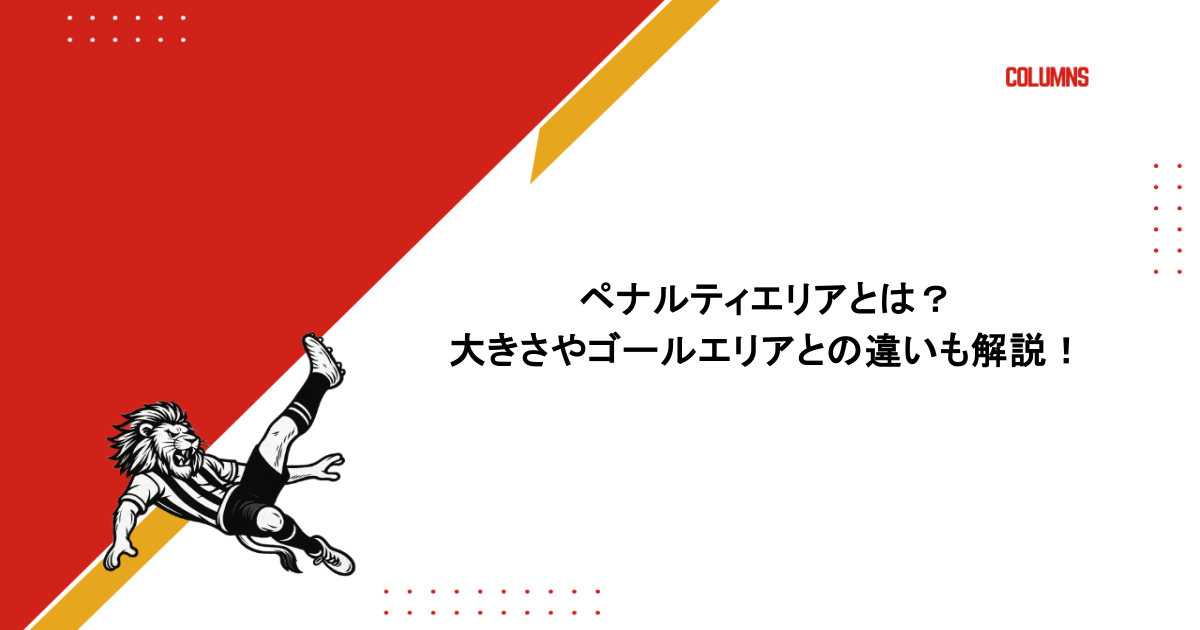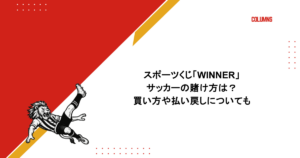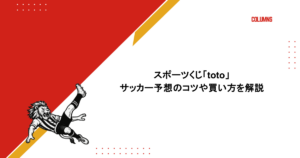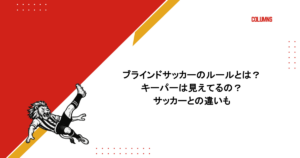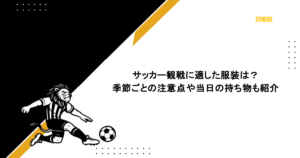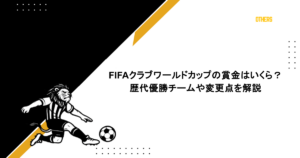サッカーにそこまで詳しくない人でもオフサイドやペナルティエリアという言葉を聞いたことがあると思います。しかし、ペナルティエリアの大きさやゴールエリアとの違いについて詳しく知っている人は少ないのではないでしょうか。
また、サッカーをプレーする上で、ペナルティエリアとゴールエリアでどういったことに気を付けた方がいいのかも気になりますよね。
そこで今回は、ペナルティエリアとはどこを指しているのか、大きさやゴールエリアとの違いを解説していきたいと思います。
ペナルティエリアとは?大きさは?ファウルしてはいけない?
サッカーの解説などでペナルティエリアという言葉をよく聞くと思いますが、どういった場所を指しているのでしょうか。
ペナルティエリアとは、両サイドにある16.5×40.32mの範囲を指しています。ペナルティエリアは得点の確率が高くなる場所で、守備側の選手は慎重にプレーをしなければなりません。
また、ペナルティエリアはファウルやハンドを取られてはいけない場所ですが、実際にジャッジが下された場合にはどのようなことが起きるのでしょうか。
PK
ペナルティエリア内で守備側の選手が攻撃側の選手を倒してしまったり、故意に手を使ってシュートなどを防いだりした場合には、PKを取られてしまうことがあります。
ビデオでプレーをチェックするVARが導入されるまでは、攻撃側の選手がわざと転倒するシミュレーションやハンドなどが見逃されることがありました。しかし、VAR導入後はそういったミスジャッジが減っていますが、ハンドの適用範囲が曖昧で、ストレスを抱えてプレーする選手が少なくありません。
間接フリーキック
多くの人がGKはペナルティエリア内で手を使うことができるということを知っていると思います。
しかし、味方選手からのパスをGKがキャッチした場合は、間接フリーキックが適用されてしまうので、注意しなければなりません。ちなみに、味方選手がヘディングしたり、偶然、体に当たったボールはキャッチしてもOKです。
間接フリーキックは一度、味方選手にパスを出してからではないとシュートすることができませんが、ペナルティエリア内はゴールまでの距離がかなり近いので得点機会のチャンスとなります。
ペナルティエリアとゴールエリアの違いは?
ペナルティエリアの範囲やファウルが起きた場合については分かりましたが、ゴールエリアはどこを指しているのでしょうか。
ゴールエリアはペナルティエリアの中にある範囲を指しており、ゴールポストがある5.5m×18.32mが大きさとなります。
それでは、ペナルティエリアとゴールエリアの違いを詳しくみていきましょう。
ペナルティエリア
先ほどペナルティエリア内でファウルが起きた場合について説明しましたが、GKはキャッチしてから6秒以内でボールを放さなければなりません。このようなルールが設けられているのは、リードしているチームが意図的に時間稼ぎすることを防ぐためです。仮に、6秒以上ボールを持っていた場合はイエローカードが提示されてしまうので、注意しましょう。
ゴールエリア
ゴールエリアが使用されるシーンは、ゴールキックを蹴るときです。GKはゴールエリア内であれば、自分の好きな位置にボールをセットすることができます。
また、GKはゴールエリアに入ってシュートをストップすることができますが、ボールがラインを完全に越えていた場合は得点が認められてしまうので、位置を把握しなければなりません。実際にプロの選手でもゴールエリア内でボールをキャッチをし、ラインを越えてしまったというケースもあるので、注意しましょう。
まとめ
今回はペナルティエリアとはどこを指しているのか、大きさやゴールエリアとの違いを解説してきました。
ペナルティエリアとゴールエリアの大きな違いは大きさやプレー再開時にボールを置くことができるかなどです。
サッカーを観るときでもプレーするときでも重要になってくるのはペナルティエリアですが、ゴールエリアの役割について知っておくことも重要ではないでしょうか。
今後はペナルティエリアとゴールエリアにも注目して、観戦してみても面白いかもしれませんね。